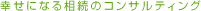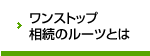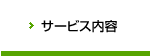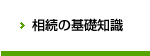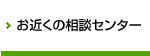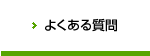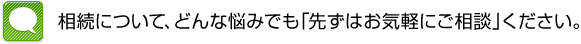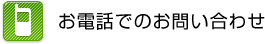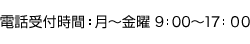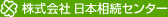3月号「相続手続きに役立つ情報」
2025.03.03 
相続手続きを行う際は、相続人や財産を確定する必要があります。相続人の確定や財産の調査に大変な手間と時間がかかりますが、相続人や財産調査に役立つ制度を上手に活用することもできます。今回は、これらの制度を改めてご紹介するとともに、今後予定されている制度についても言及したいと思います。
1.相続人の確定に役立つ制度
(1)戸籍証明書等の広域交付制度
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍証明書等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等)を請求できるようになりました(広域交付)。これにより、本籍地が遠方にある方も、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村町の窓口でまとめて請求できるようになります。
広域交付で戸籍証明書を請求できるのは、本人、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)です。
兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪の戸籍謄本等は請求することができません。また、戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票、コンピュータ化されていない戸籍も取得することができません。
この制度を利用する場合には、郵送や代理人による請求はできず、請求できる方が市町村等の戸籍担当窓口にて顔写真付きの身分証明書を提示の上請求しなければなりません。また、その日に取得できるとは限らず、日数を要する場合もあります。
(2)法定相続情報証明制度
相続人を確定するためには、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等を準備する必要があります。銀行・証券会社の相続手続きや不動産の相続登記の際には、戸籍謄本等の原本の提出が求められます。場合によっては郵送等での手続きになるため、原本を郵送して手元にない間は他の金融機関等の手続きをすることができず、全ての手続を終えるまでに多くの時間が必要になるケースがありました。
そこで、「法定相続情報証明制度」を活用すると、相続手続きを効率良く行うことができます。この制度は、相続人が相続関係を一覧にした図(法制相続情報一覧図)及び戸籍謄本等を登記所に提出し、一覧図の内容が相続関係と合致していることを登記官が確認した上で一覧図に認証文が付され、その写しが被相続人の法定相続情報として交付(無料)される制度です。複数枚取得しておくと、相続手続きを行う際に大変役に立ちます。詳細については、法務省ホームページを参照ください。
なお、令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号(11桁)を記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるなど、より活用の幅が広がっています。
2.財産調査のために役立つ制度
「生命保険契約照会制度」は2021年7月1日から開始した制度で、被相続人が加入している生命保険がわからない場合に、生命保険協会に生命保険の契約の有無を照会することができる制度です。利用料は、調査対象となる方1名につき3,000円です。詳細については、一般社団法人生命保険協会のホームページをご覧ください。
今後予定されている制度として、「預貯金口座付番制度」が挙げられます。預貯金口座への付番とは、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナンバーを付番することができる制度です。
この預貯金口座への付番によって、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになるというメリットがあります。詳しくは、デジタル庁のホームページをご参照ください。
また、「所有不動産記録証明制度」も2026年2月2日から利用できる予定です。この制度は、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官が、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です(不動産登記法第119条の2)。これにより、被相続人が有する全国の不動産を一括調査ができるようになります。詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
このように、相続手続きの際に役立つ制度を活用することで、相続手続きをスムーズに行うことが可能です。しかし、やはり相続手続きは多岐にわたり、時間と手間がかかることが多いです。専門家に任せるという方法も一つの有効な方法だと思います。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二