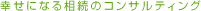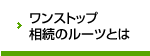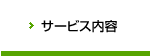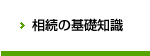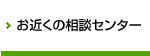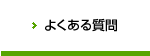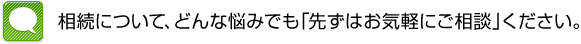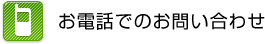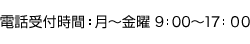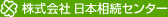4月号「法定後見制度と任意後見制度」
2025.04.01
後見制度とは、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことにより、認知症や精神障害等の理由により判断能力が不十分な人を保護・支援する制度をいいます。判断能力が不十分な人とは、例えば、認知症などにより、身の回りの世話のための介護サービスや施設入所の手続を自分で締結することが難しい人をいいます。
成年のための後見制度は、「法定後見制度(成年後見制度)」と「任意後見制度(任意後見契約)」の二つがあります。
「法定後見制度」とは、判断能力の程度等本人の事情に応じて、裁判所へ請求することにより後見人が選任され、本人のための後見が開始する制度をいいます。具体的には、精神上の障害により事理を弁識する能力が欠けていることが通常の状態にある人には「後見」(民法第7条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人には「保佐」(同第11条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人には「補助」(同第15条)が、選任されます。なお、事理を弁識する能力とは、およそ自分の行為の結果を判断する能力をいいます。
これに対し、「任意後見制度(任意後見契約)」とは、委任される人(委任者)の判断能力が不十分となった場合に備えて、お元気なうちに、あらかじめ信頼できる方(自然人・法人)に後見人になってもらう契約を締結しておくことをいいます。
両者で異なる点は、自分が希望する人にサポートをしてもらえるかどうか、という点にあります。「法定後見制度」では、裁判所が法定後見人を選任するため、必ずしも当事者が希望する方が選任されるとは限りません。他方、「任意後見制度」では、本人がお元気なうちに、この人に自分の身の回りのお世話に関する契約ごとを頼みたい、という自分の意思を反映する任意後見契約を締結することにより、あらかじめ希望する方を選任することができます。また、任せたい範囲(代理権の範囲)についても、具体的に代理権目録に記載することにより、柔軟に対応することができます。
また、判断能力はあるものの、年齢を重ねたり、病気になるなどして体が思うように動かせなくなる等の「もしも」の場合に備えて、財産管理等をお願いする委任契約を任意後見契約と組み合わせて同時に締結することができます。これは、本人の判断能力があるうちは委任契約により対処し、その後本人の判断能力が低下した場合には、裁判所へ任意後見監督人を選任し任意後見契約の効力を発生させ、これまでの委任契約の効力を失効させるという、いわゆる「移行型」の契約です。
このように、自分の希望する形のサポートを受けることができるようにあらかじめ備え、契約内容で柔軟に対応することができる点が、任意後見制度の特徴です。
転ばぬ先の杖の一つとして、任意後見制度をご検討されることも有効だと思います。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二