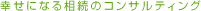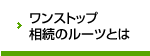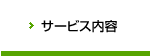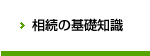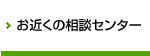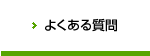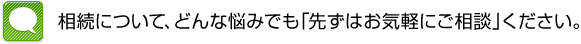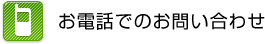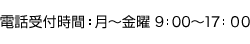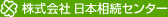12月号「相続の備えで大切なこと」
2021.12.01
先月号では、老後であっても明るくアクティブな人生を送るための1つのヒントとして「ブレインパフォーマンス」をご紹介しました。今月号では、認知機能の低下に伴うリスクと相続というテーマで相続の備えで大切なことについてご紹介したいと思います。
年齢を重ねるにつれて体の衰えを実感することがありますが、脳の健康については、あまり意識されないまま年齢を重ねられている方が多いのではないでしょうか。しかし、認知機能は体と同様50代から明らかな衰えが始まるそうです。
適度な運動・歩くことを意識する、バランスの良い食事や肥満予防、適度な飲酒・禁煙、社会とのつながりを持つことなど、日々の生活の中で「ブレインパフォーマンス」の維持向上につながるライフスタイルを意識することで認知機能の低下を予防することができます。
老後の体と認知機能への不安を少しでも軽くするために、なるべく早く注意を払っておくことが大切です。他方、それでも認知機能の低下のリスクはあります。
認知機能の低下に伴い、判断能力が不十分または判断能力が欠如してしまった場合、日常生活のみならず、さまざまな法律行為の効力に影響が生じます。もし、認知症になってしまうと、法律上意思能力がない状態と判断され、子や孫への贈与契約や遺言書作成、生命保険契約締結など、生前の相続対策として有効な手段とされる各種法律行為の効力が無効とされてしまいます。
例えば、せっかく相続対策として遺言書を作成しても、遺言書の効力について争いが起こり、遺言書作成時の遺言能力(意思能力)に問題があるとして遺言が無効になる可能性もあります。
このような場合、遺言作成と同時に、認知症検査を受けた上で医師の診断書を作成してもらうなどの方法も有効な方法の1つです。
しかし、ここで大事なポイントは、「時間」を味方につけることだと思います。
意思能力に問題が生じる前、判断能力がしっかりとしているうちに、なるべく早くから相続対策に取り組むことがより大切です。前述したとおり、認知機能は体と同様、現役世代の50代から明らかな衰えが始まりますので、60代や70代の方は、時間を味方に早くから相続対策に取り組まれることをお勧めいたします。
なお、当センターでは、ご家族の幸せを実現するための相続の備えである生前対策に力を入れております。生前対策は早めに取り組めば取り組むほど、心に余裕をもって対策を講じることができます。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二