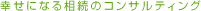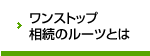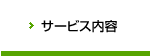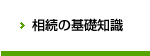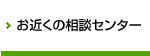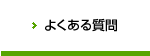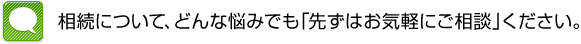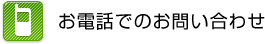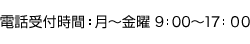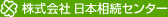8月号「おひとりさま」の相続
2023.08.01
近年、「おひとりさま」という言葉を良く耳にします。2020年の国勢調査の結果(2021年11月末政府公表)では、単身(シングル)世帯の割合が38.1%となり、この割合は上昇の一途をたどっています。高齢化が進むなか、配偶者やパートナーとの死別や離別で単身(シングル)となる人は多く、さらに若いうちから単身(シングル)で生きる「おひとりさま」を選択する人が増えてきています。
「おひとりさま」という生き方も一つの生き方だと思います。しかし、「おひとりさま」が亡くなられた場合の手続きや相続手続の準備を何もしていなかった場合に問題が発生します。
この相続ニュースでも、たびたび相続の備えが大切であること、遺言の作成が有効であることをご紹介してきました。「おひとりさま」の場合には、相続人がいないケースが多く、相続人がいる場合でも兄弟姉妹が相続人になり、相続人の人数が多くなるため合意形成が難しくなるケースも多いようです。
一番大変なのは、生涯独身で配偶者や子どもがおらず、両親も既に他界、兄弟姉妹もいない場合の「おひとりさま」です。例えば、病院に入院して手術をする場合には、病院から保証人を求められますし、生死にかかわる入院時には、延命治療を受けるかどうかの意思確認が取れないというような問題もあります。そして、「おひとりさま」が亡くなられた場合、病院や施設利用料の支払い、お葬儀(火葬のみの場合でも)費用の支払いなど、亡くなられた直後にもまとまった支払いが必要になります。さらに、相続財産を清算するために、相続財産清算人を申し立てたりしなければ、財産を動かすことすら出来なくなるため、債務の支払い、例えば家賃や生活関連費用の支払いに関して困った状況になります。
最高裁判所の調べによると、相続人不存在で国庫に入った財産額が、2021年度は過去最高の約647億円を記録したそうです(2020年度は約600億円)。この額は10年前のおよそ2倍に相当します。今後も、高齢の「おひとりさま」が増加するにつれて、国庫に帰属する遺産額はさらに増大するのではないかと考えられています。
このような困った状況にならないためにも、「おひとりさま」として生きる選択をされた方は、特に、ご自分がもしものときにどうして欲しいのか、お金の支払いに関することも含めて準備されておく必要があります。このことは「おひとりさま」に限ったことではありませんが、「おひとりさま」の相続対策は大変重要です。
8月は各地でお盆を迎える季節です。故人を偲びながら、自分のもしものときのことを考えてみてはいかがですか。現在の財産状況の整理を踏まえて、今後どのように生きたいのか、もしもの場合には誰に手続きをお願いしておくのかなど具体的に検討し、準備しておきましょう。
何をどのようにすればいいかわからない方は、当センターまでお気軽にご相談ください。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二