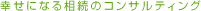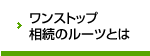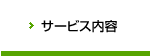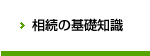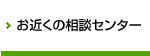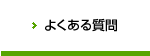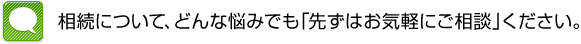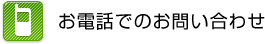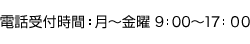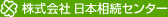9月号「生前整理・遺品整理はお早めに」
2020.09.01
まだまだ暑さが厳しいですが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
この暑さの中で、熱中症と新型コロナウイルスの予防のためのマスク着用のバランスをとることは難しいところです。まだ感染者が増えつつありますので、引き続き身を守る備えとして、「三密(密閉・密集・密接)を避ける」、「マスクや手洗いを徹底する」、「日頃から規則正しい生活を送る」ことを出来る限り心がけ、自分や大切な家族の健康を維持していきましょう。
備えの大切さは、8月号の相続ニュースでもお伝えしておりますが、9月号でも、備えの大切さの1つとして、「生前整理・遺品整理はお早めに」という内容でお伝えしたいと思います。
8月号にて、「終活」とは、人生のエンディングを自分らしく迎えるため、しっかりと準備することと一般的に解され、主に遺言書を書く前段階のきっかけになると考えられています。また、残された家族側も、エンディングについて本人の願いを知り、それを実現可能であれば協力することができますます。さらに、ご本人・ご家族の双方が無駄な気遣いやお金を使わずに済むメリットがあるとご紹介しました。
また、「終活」として早めに「生前整理」に取り組むことも、結果的にみるとご本人・ご家族の双方が無駄な時間やお金をかけずに済むケースが多いように見受けられます。
例えば、実家に父母や小さい頃からの子どもたちの荷物がそのまま残っていて、ご両親が亡くなられた後に実家を売却したいと考える際に、片付けに頭を悩まされ、結果的に処分を業者に依頼し、処分費も合わせると結構な金額になってしまうケースも多くあります。
この場合も、「時間」がキーワードとなります。ご本人が生前に今後の生活に必要最小限の物を残す計画を立て、地道にコツコツ整理・処分していれば、何が重要で何が重要ではないのかの選別がされるので、残された家族もいわゆる形見分けという形で遺品を引き継ぐことが可能になります。しかも、処分費も日頃のゴミ分別に合わせて少しずつ取り組むことで、業者依頼分の費用を浮かせることができ、お金も効果的に使うことができます。
また、同じく「遺品整理」も早めに取り組むことで、実家の早期売却による固定資産税負担軽減などの費用を無駄に支払わずに済むことになります。
残された家族がそれぞれ自宅を既にもっているご家族は尚更のこと、ご実家の整理を早めにお願いする、もしくは一緒に取り組むなどして、親御さんに早めの「生前整理・遺品整理」を促すことも大切になってくると思います。
終活を含め、何をどのようにすれば円満な相続を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二